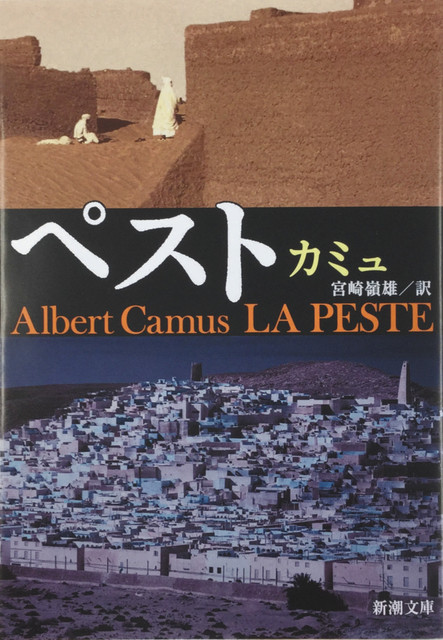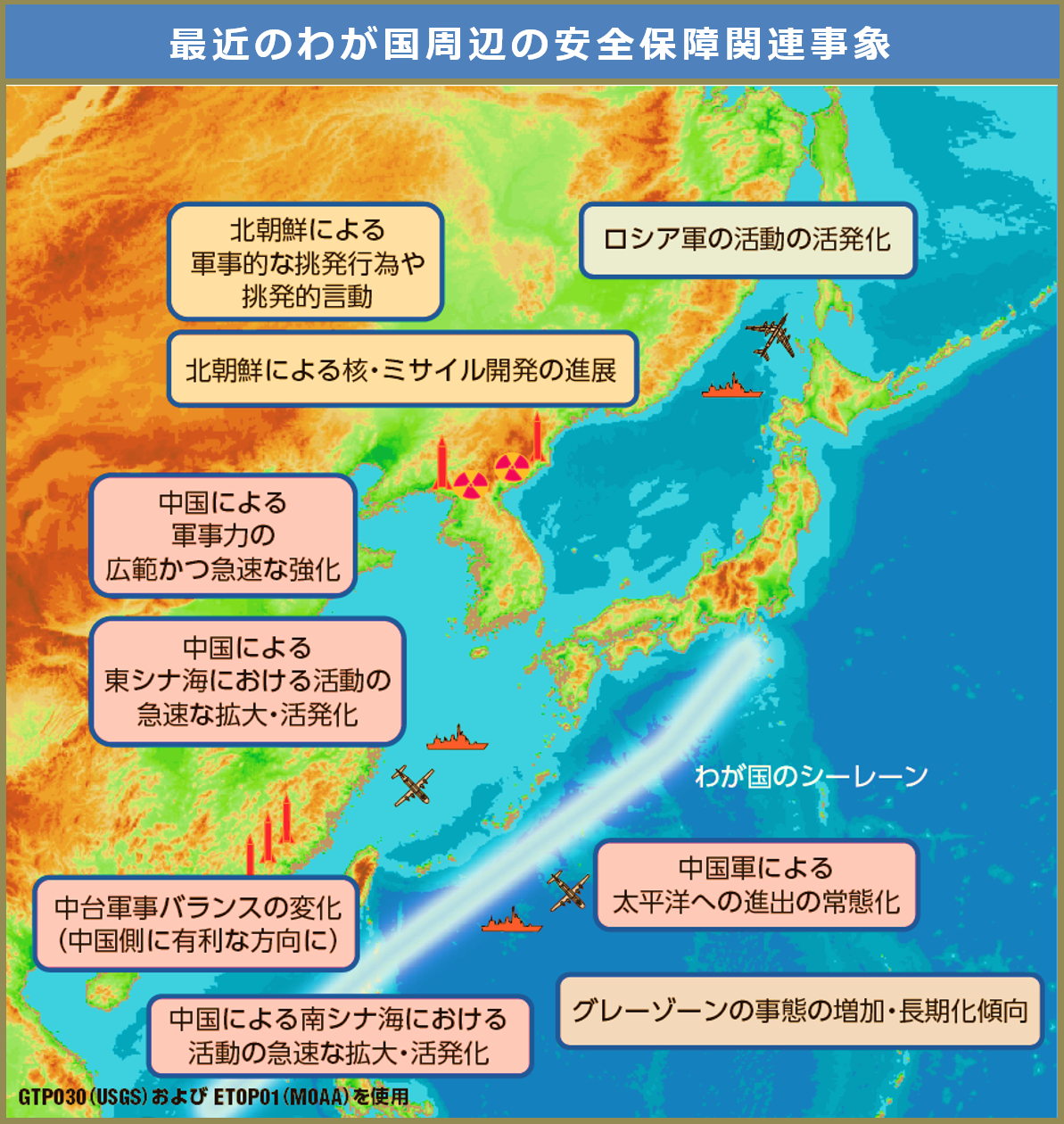En termes plus modernes, plus théoriques, tenant compte de ce que la psychanalyse nous apprend du mécanisme du désir, nous pourrions dire ceci : la fonction dogmatique consiste, dans une société, à prendre acte du désir impossible à combler et de la nécessité de reconnaître, par les moyens appropriés à la reproduction de l’espèce, que la dimension du manque est la dimension même des jeux d’institutions. Pourquoi ? Parce que les humains, demeurant liés jusqu’à la mort à l’enfance de leur désir, c’est-à-dire, comme le démontre l’expérience clinique du mythe œdipien dans la cure, au désir de leur enfance qui en tout premier lieu se rapporte au désir de la mère, doivent entrer dans la parole de telle sorte que cette parole fasse aussi lien social. Les jeux d’institutions sont les jeux de la Loi, de cette Loi qui par un interdit fondamental introduit les humains à l’espace du manque, en les faisant sortir du désir univoque de la mère. La loi est une fonction, assumée pour chaque sujet dans la triangulation œdipienne par le père, ce que nous appelons un père. Tout le dispositif juridique repose sur ces fondements-là, parce que là se joue le principe d’autorité et de légitimité. Les institutions ont donc affaire prioritairement au mécanisme du désir humain, à la reconnaissance généalogique. Cela doit être tenu comme un fait primordial, afin d’étudier l’extraordinaire flexibilité du droit romain dans l’histoire occidentale et comprendre que cette histoire, elle aussi, est un phénomène de structure.